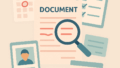私が実際に督促から差押えまでの案件で用いたファイル構成をベースに、弁護士が受け取って即行動できる最短テンプレをまとめます。書類名と並び順を揃えるだけで対応が速くなる実感がありました。
これは筆者の体験であり、すべての事例に当てはまるとは限りません。
筆者の体験であり一般化不可
目的と使い方
目的は「弁護士が受け取って即時に方針決定・手続着手できること」です。A/B/Cの優先度に分け、渡し方と注意点を明確にします。内部の時系列・重要度整理は「訴状送達後の弁護士相談前に自分でできる証拠整理テンプレ(時系列・重要度・渡し方)」を参照すると効率的です。
A:最重要(弁護士が即確認すべきファイル)
- 表紙/目次(簡潔に「事件名・依頼者情報・ファイル構成」)
- 催告・督促関連(PDF、原本スキャン)—「支払督促」受領の有無を明記
- 送達証明/配達記録(配達日時が判るもの)—受領からの期限管理(例:「受領後2週間」等)
- 債務の発生日を示す契約書・請求書(時系列で並べる)
- 直近の入金履歴(銀行明細の該当部分、赤線で該当行を示す)
- 差押え通知・強制執行関連(既に差押えがある場合)
B:高優先(弁護士が判断材料としてすぐ見たいもの)
- 取引履歴(時系列、CSV+要約PDF)—重要取引はコメント付
- 督促のやり取り(メール/SMSのスクショ、日時順)
- 支払猶予や交渉記録(メモ・録音の書き起こし)
- 過去の類似対応メモ(自分で行った時効の援用や異議申立ての経緯)
C:補助資料(事件対応後や追加確認用)
- 契約関連の全原本(スキャンで可、原本の所在を明記)
- 家計簿・収支一覧(任意・交渉資料)
- 関係者の連絡先一覧と役割メモ
- その他参考資料(領収書、写真等)
渡し方とファイル命名ルール
私の経験上、以下が弁護士の作業効率を上げました。フォルダ階層は「案件名/優先度/日付-内容.pdf」のように統一します。PDFは可能な限りOCR済みとし、重要ファイルにはタイムスタンプと作成者メモを添えてください。渡し方はUSB+暗号化ZIPか、期限付きクラウド共有リンク(アクセスログ有)を推奨します。
注意点(手続き目線のキーワード)
- 催告期間や対応期限は事件により異なりますが、私の経験では「催告 最長6ヶ月」が交渉の目安になることがありました。
- 訴状・支払督促が来た場合、応答の選択肢(異議申立て、承認=更新(完成猶予)の扱い等)を弁護士がすぐ判断できるよう、該当文面の抜粋を最上位に置きます。
- 時効の検討がある場合は、「時効の援用」に関する既往のメモをBに入れてください。
最終チェックリスト(弁護士渡し前)
- 目次があり、弁護士が第一読で重要書類に到達できるか
- 主要期限(受領後2週間等)を赤字で明示しているか
- ファイルはOCR済・閲覧可能・アクセス権が明確か
- 差押えや支払督促など緊急性のある通知はAにまとめているか
必要に応じて「差押え後の証拠パッケージ作成チェックリスト:弁護士が即対応できる優先手順」や「訴状での承認回避実例集と安全な応答テンプレ集何が承認となるかの解説付き」を参照すると、弁護士との初回打合せがさらに短縮できます。
▼自己紹介/体験まとめ:https://myhome-black.net/syokai/