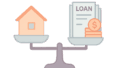自己破産と個人再生で住宅を残すか手放すかは生活軸で大きな違いが出ます。ここでは具体事例を交え、残存可否、想定費用、所要期間、必要書類を比較し、検討材料を整理します。
住宅を残せるかの大枠
実務感では、個人再生(住宅ローン特則を利用)が住宅を残す選択肢になりやすく、自己破産は自宅処分に向かうことが多いと感じます。個人再生ではローンだけ別扱いにして再生計画で残す一方、自己破産では担保付き債務(住宅ローン)は原則、担保権実行→競売・任意売却となりやすいです。ただし債権者との交渉や残債の状況によって結論が変わるため、一概には言えません。
費用の比較(目安)
- 個人再生:弁護士費用+裁判所手数料でおおむね50万〜100万円程度(ケースによる)
- 自己破産:弁護士費用+予納金でおおむね30万〜70万円程度(財産の有無で変動)
- 住宅処分関連費用:任意売却や引越し費用、残債処理費用が別途発生する可能性
期間の比較(目安)
- 個人再生:申し立てから終了まで概ね6〜12ヶ月程度になることが多いです。
- 自己破産:同じく6〜12ヶ月、場合によっては予納や異議対応で延びます。
- 実務上の書類や通知対応は時間が重要で、裁判所や債権者からの書面で示される期日は厳格に扱う必要があります。裁判所書類への対応目安として「受領後2週間」を意識する場面があります。
必要書類(代表例)
- 住民票、収入証明(源泉徴収票・給与明細)、課税証明書
- 住宅ローンの残高証明書、金銭消費貸借契約書の写し
- 登記事項証明書(不動産登記簿謄本)、光熱費や保険料の領収書
- 借入一覧、カード明細、督促状の写し(支払督促や催告が来ている場合)
具体事例で見る比較
事例A:個人再生で住宅を残したケース(夫婦・共働き)
状況:住宅ローン残債3000万円、住宅評価2800万円、年収600万円。ローン滞納は数ヶ月。対応:弁護士と相談し個人再生の住宅ローン特則を利用。再生債権は整理しつつ、住宅ローンは従前どおり支払いで維持。費用は弁護士費用約70万円、手続き期間9ヶ月程度。結果的に住替えをせずに継続可能になったが、ローン返済計画の調整が必要だった。
事例B:自己破産で住宅を手放したケース(単身)
状況:住宅ローン残債1800万円、評価1600万円、年収200万円、生活費圧迫。対応:弁護士と自己破産を選択。担保付き債務は原則処分対象となり任意売却で処理、引越費用などを用意。手続き費用は約40万円、処理期間6〜8ヶ月。結果として住宅は手放し、住宅ローン債務は免責されたが居住は終了した。
実務上の注意点と裁判外対応
債権者からの催告は厳しいため、時には「催告 最長6ヶ月」といった猶予期間が示される場面もあります。支払督促が出された場合は「異議申立て」できる余地があり、請求に対しては「時効の援用」を検討する場面もありますが、住宅ローンのような長期債務では適用判断が難しいため専門家と相談するのが現実的です。なお、ブラックや債務整理がある場合でも、条件がそろえば住宅ローンが通る可能性はあります…(関連ページ参照)。また、住宅ローンや個人債務での催告対応は書面の受け取りや期限の扱いで迷うことを整理します。(関連ページ参照)
まとめと次の一手
経験上、住宅を残したいなら個人再生の検討が一歩目になりやすく、手放して整理するなら自己破産が選択肢になります。費用や期間、書類はケースで変わりますので、まずは書面や督促状を揃え、専門家に現状を見せて相談することをおすすめします。最終判断は状況に応じて慎重に。承認=更新(完成猶予)の扱いなど裁判所手続きの細部は専門家の助言が有用です。
▼自己紹介/体験まとめ:https://myhome-black.net/syokai/