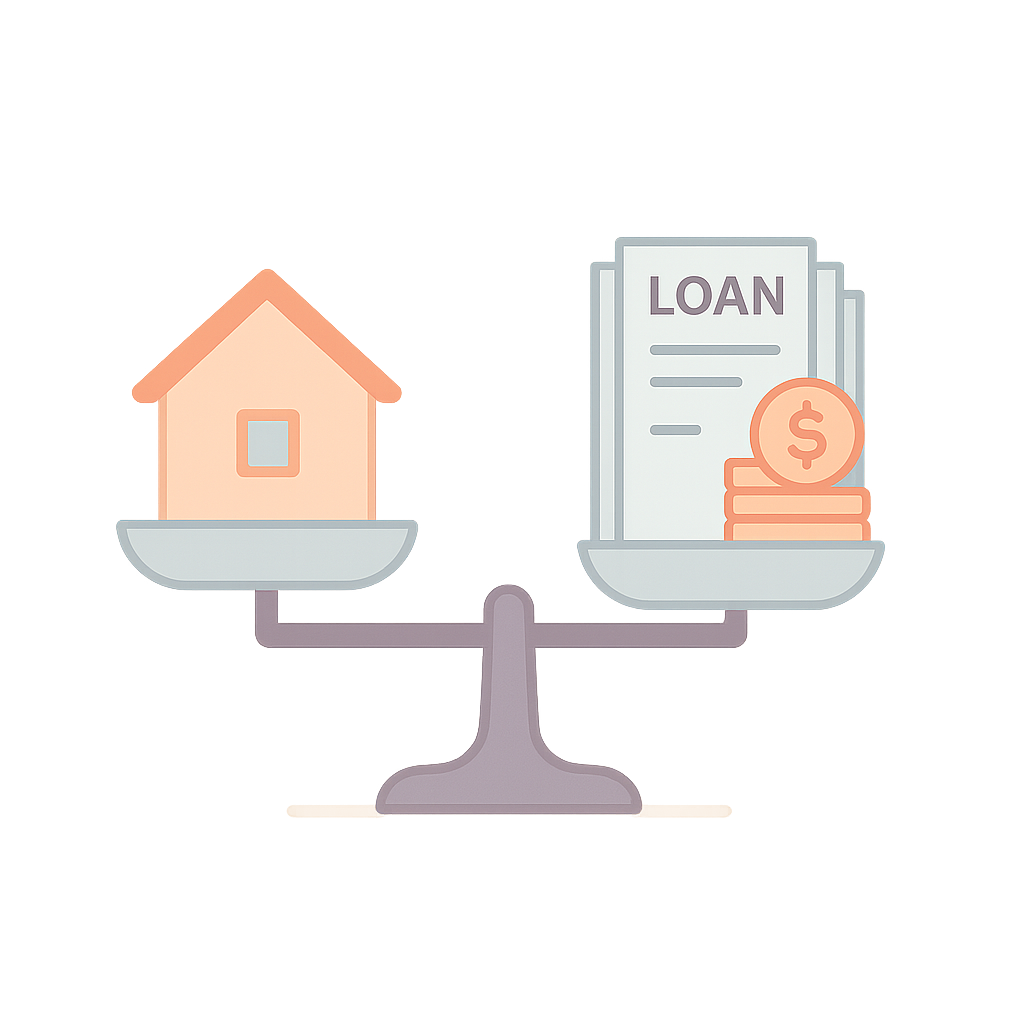自己破産と個人再生で住宅を残すかは、ローン残高・担保評価・手続きの選択で変わります。実例を交えて費用、期間、必要書類を整理し、判断の軸を示します。
概要と結論の出し方(経験ベース)
私見では、住宅を残す意思が強くローンを続けられる見込みがある場合は個人再生が検討されやすく、支払不能で債権調整が主目的なら自己破産で手放す決断になることが多いです。ただし債権者の対応や担保評価で結論が左右されるため、各要素を数値で比較すると判断しやすくなります。
住宅を残すケース:個人再生(事例)
代表的な事例
年収400万円、住宅ローン残高2,500万円、他借入300万円のAさん。個人再生で住宅ローンを別扱いにしつつ、再生計画で他の借金を圧縮し、住宅は維持する選択をした例があります。
費用と期間
- 費用(私の依頼経験): 弁護士費用と裁判所手数料でおおむね30万〜60万円程度。
- 期間: 申立てから計画の承認=更新(完成猶予)まで概ね6〜12ヶ月が標準例。
- 実務メモ: 債権者との調整や抵当権処理で想定より時間がかかることがある。
必要書類(主要)
- 収入証明(源泉徴収票、確定申告書)
- 住宅ローン契約書、残高証明
- 資産目録、生活費明細
住宅を手放すケース:自己破産(事例)
代表的な事例
Bさんは収入減少でローン滞納が続き、住宅ローン残高1,800万円、他債務600万円を抱え自己破産を選択。担保付き債権は競売で処理され、住宅を手放す結果になった経験があります。
費用と期間
- 費用: 同様に弁護士費用がかかり、手続き簡易化の有無で20万〜50万円程度の幅。
- 期間: 申立てから免責まで6〜9ヶ月が一般的だが、異議申立てや上訴があると延びる。
- 実務メモ: 債権者の「支払督促」や競売手続きとの兼ね合いで迅速な対応が必要になる。
必要書類(主要)
- 財産目録、借入一覧、預貯金通帳の写し
- 住宅の登記事項証明書、ローン残高証明
- 生活実態を示す資料(家計簿など)
実務上の注意点とタイミング
債権者からの書面は受領後2週間を目安に対応すると安心です。滞納が続くと支払督促や強制執行の手続きが進み、銀行側の催促 最長6ヶ月の間で事態が動くことがあります。手続きの選択は、担保価値・残債・今後の収入見込みを組み合わせて判断します。
争い・異議対応と時効の検討
督促や差押えに対しては異議申立てで対応する道があり、支払督促に対する対応は重要です。債務について時効が成立する場合でも、時効の援用が可能かはケースバイケースで、専門家の確認が必要でした。
判断のためのチェックリスト(経験則)
- 住宅の担保価値とローン残高の差を確認する(差が大きければ残しやすい)
- 現在の収入でローン返済を続けられるかを試算する
- 手続きにかかる費用と期間を見積もる(個人再生は長く費用も高め)
- 債権者からの通知は速やかに確認し、必要なら異議申立てを検討する
最後に(決定の進め方)
経験上、まずは書類を揃えて概算の差額試算を行い、個人再生で残す場合と自己破産で手放す場合のキャッシュフローを比較すると判断しやすくなります。詳しい手続きやローン承認の可否は、個別に確認することをおすすめします。
▼自己紹介/体験まとめ:https://myhome-black.net/syokai/