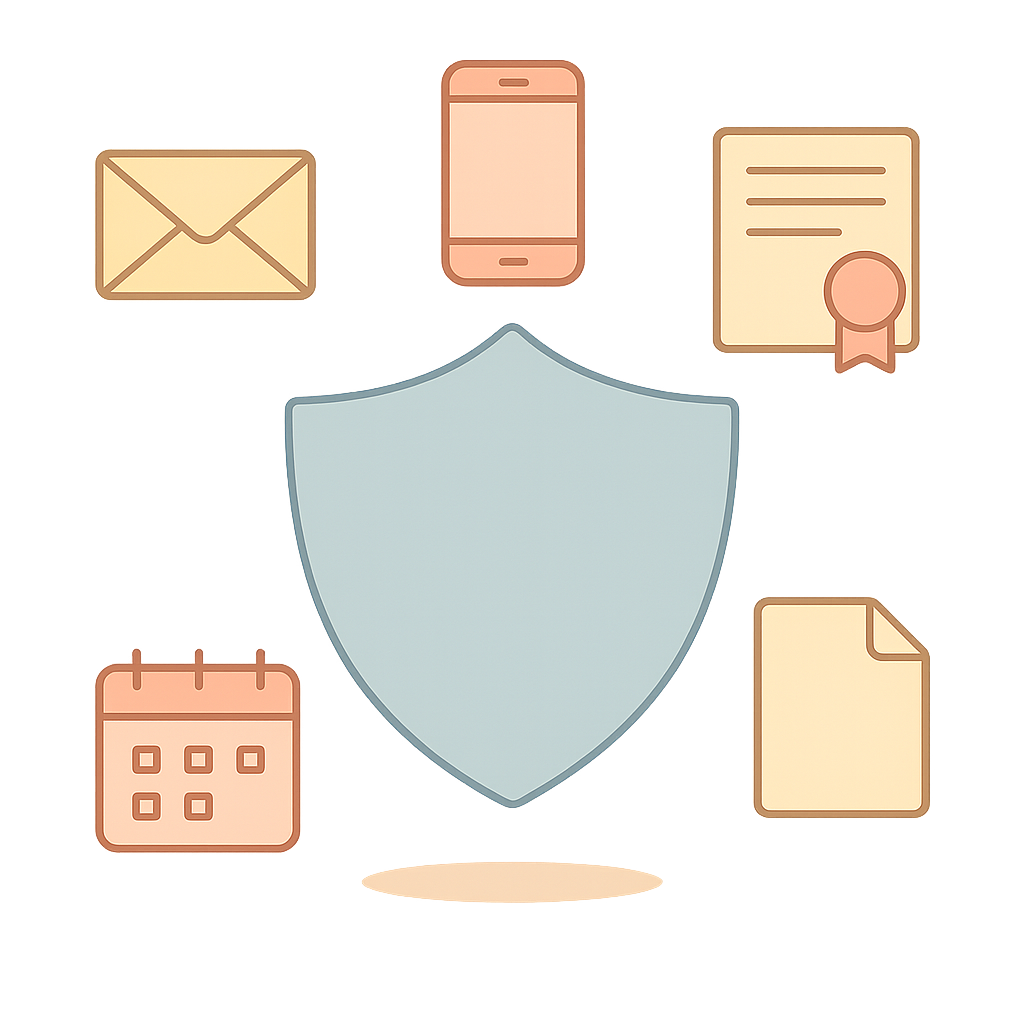催告にまつわる説明で「催告 最長6ヶ月」といった表現を耳にすると、時効が止まると誤解しやすいように思います。保証人に請求が及ぶ前に、債権者が取りうる催告手段とタイミングを把握し、記録保存と応答方針を事前に整えておくと被害を抑えやすくなります。
「催告 最長6ヶ月」とは何が誤解されがちか
現場でよく聞くのは「催告があれば時効が止まる」「催告=最大6ヶ月の猶予」といった理解です。実務経験からは、この表現は文脈次第で意味合いが変わりやすく、断定的に受け取ると危険に思います。催告そのものが自動的に時効を完全停止させるわけではなく、契約や法的手続きの種類、催告の方法によって効力が異なる場合が多い印象です。
債権者が保証人に請求する前に取りうる主な催告手段とタイミング
- 電話やメールによる催促:初期段階でまず連絡を試みることが多く、記録が残りにくい点に注意が必要です。
- 書面(通常郵便)での督促:履歴が残りやすく、契約書上の催告条項の発動に使われることがあります。
- 内容証明郵便:送付記録が強く残るため、債権者が法的対応を示唆する際に使われやすいように思います。
- 支払督促・裁判書類の送付準備:保証人への直接請求前に、債務者に対して法的手続きの準備を進めることがあり、それが保証人に伝わるケースもあります。
- 債権譲渡や債権回収会社への委託通知:第三者が関与すると連絡方法や速度が変わることが多いです。
催告と「完成猶予」の関係をどう見るか
「完成猶予」という言葉は契約条項や実務で使われる場合がありますが、契約ごとに意味が異なりうるため、催告が直ちに義務履行を覆すわけではないと考えるのが安全です。催告は履行を促す手段であり、一定の猶予期間を設ける旨が書面で示されれば、その期間内の交渉余地が生まれることがありますが、法定の時効中断や停止として単純に換算するのは避けたほうが良いように思います。
保証人が請求を受ける前に実行すべき具体的手順
- 記録の一元化:契約書、返済履歴、口座振替の明細、受け取った書面やメールを日時付きで保存します。スクリーンショットや受領証も有効です。
- 通話ログの記録:電話が来たら日時と相手名、要旨をメモし、可能なら録音(法令遵守)を検討します。
- 初期応答方針の設定:不用意に支払義務を認める発言を避け、まずは「書面での請求を求める」旨を伝えるテンプレートを用意しておくと安心です。
- 内容証明の活用検討:相手の主張に争いがある場合や事実関係を確定させたい場合、内容証明で質問や回答期限を設定することが役立つ場合があります。
- 専門家への相談窓口を事前確保:弁護士・司法書士に相談すると証拠の取り方や応答文面の方針が明確になります。初期相談で方針だけ決めるのも一案です。
応答テンプレート例と記録保存の注意点(実務的配慮)
実務では「まず事実確認を請求する」「支払いの意思表示は控える」といった短文をメールや書面で送ることが多く、やりとりは全て保管します。例えば「ご連絡の件につき、契約書面と返済履歴の提示をお願いします。到着後、改めて検討します。」といった表現が使いやすいように思います。なお、削除されたSNSや口頭でのやりとりは証拠化が難しいため、可能な限り書面化する習慣をつけると後で楽になります。
最後に、催告に関する説明は契約内容や個別事情で大きく変わることが多く、断定的な情報だけで動かず、記録を残しつつ専門家に相談する準備をしておくのが実務的だと感じます。
▼自己紹介/体験まとめ:https://myhome-black.net/syokai/